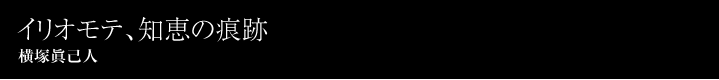![]()
2014.04.01
機織り機とともに西表島に嫁入りしたものの……
その歴史が500年以上といわれる西表島の伝統行事「節祭(しち)」で使われている衣装は、祖納集落在住の染織作家・石垣昭子(いしがきあきこ)さんが30年以上の歳月をかけて復元したものだった。石垣昭子さんは竹富島出身で、美大を卒業後、京都で染色の修行をされ、夫で西表島・祖納集落出身の石垣金星氏と開設した「紅露工房」で染織の制作を続けている。
昭子さんが西表島で夫とともに生活をするようになったのは、1980年頃だった。その時に竹富島から機織り機の高機(たかばた)を持ち込んだ。昔から竹富島では、機織り機は嫁入り道具で、生活の中で布を織る事が女として当たり前の仕事だった。機織り機が一人1台という環境で、昭子さんは育った。ところが、西表島へ来てみると、誰一人として機織りをやっている人がいない。村の女性に、機織り機はどうしたと聞くと「薪にして燃やしたさあ」という答えが返ってきたときは、自分の耳を疑った。
炭鉱の繁栄によって途絶えてしまった西表島の「衣」の文化
民家の中を見わたすと、麻糸を紡ぐ道具だけがかつて機織りをしていたという事実を物語っていたが、西表島の「衣」の文化はすでに絶滅していた。炭鉱の時代に急速に衰退していったのだという。八重山諸島の中で、唯一炭鉱があったのが西表島だ。炭鉱のおかげで、たくさんの物資が本州や九州からダイレクトに届き、今は「秘境」と呼ばれる西表島が、その当時は地方都市レベルでさまざまな物が手に入る場所だったようだ。
西表島の炭鉱事業は1886年(明治19年)から第二次世界大戦の終戦まで、およそ60年間続いた。炭鉱は祖納集落がおかれている島の西部に集中していたため、村との交流もあった。村人にとっては、炭鉱へ農作物を持っていけば買ってくれるし、そこはさまざまな物が手に入る便利な場所であった。村人は炭鉱と商売をするために公用語で話をするようになり、それが世代交代していくうちに方言が急速に失われていく大きな原因になったともいわれている。さらに、日用品や衣料も簡単に手に入ったので、手間のかかる手業の物作りも、機織りも、誰もやらなくなっていった。生活の文化が大量生産、大量消費の波にのみ込まれてしまった時代だった。見た目に色鮮やかで安価な化繊の布に駆逐され、西表島の「衣」の文化はその時から急速に途絶えていった。
神女から頼まれた打ち掛け織り
そんな時代でも、先祖代々から稲作で生計を立てきた祖納集落の人々には、稲作儀礼が根強く残っていて、節祭や豊年祭などの伝統的な行事は続けられてきた。しかし、染織家である昭子さんの目から見ると、伝統行事で使われる衣装は残念なものばかりだった。
昭子さんが西表島で生活をするようになってしばらくして、神女から打ち掛けを織ってほしいと頼まれた。これが「衣」の文化を復元するきっかけとなった。神女の打ち掛けを見せてもらうと、確かに袖がぼろぼろだった。白い麻には霊力が宿ると信じられていて、神女にとって打ち掛けは大切なもの。神女は自分で紡いだ麻の糸だけは持っていたという。神女の家の庭には苧麻が栽培されていた。昔から神女は、苧麻を栽培し麻糸を紡いで、自分の打ち掛けは自分で織るというのが慣わしだったようだが、機織り機はどこにも見あたらない。庭に生えている苧麻が歴史を物語っていた。
「ミルク神」という祭りの神様の衣装を復元
ちょうどそのころ、夫の金星氏が49歳で節祭のミルク神に選ばれた。ミルクになれるのは、49歳の村人や村出身者の男性と決まっている。昭子さんが公民館に保管されているミルクの衣装を確認すると、それは化繊の布で作られていた。自分の夫の晴れ舞台という事もあり、神様の衣装の復元を買って出た。先ずはミルク様がどこから来たのかを調べてみると、ベトナムであることを知り、そうであれば苧麻や芭蕉ではなく、シルクであると判断した。それから蚕を飼い、その糸から布を作った。
あとは染め色だ。基本的にミルクの衣装は黄色だが、同じ黄色でもさまざまある。一日中野外で太陽光線にさらされるので、堅牢かつ自然光に一番はえる色を考えていた。昭子さんの故郷の竹富島では、ミルクの衣装はヤエヤマアオキという植物で染めていることを知っていた。ヤエヤマアオキは赤味の強い黄色に染め上がるそうだが、昭子さんは西表島の伝統色の一つであるフクギの黄色をそこに混ぜた。フクギは同じ黄色でもレモンイエロー。いくつかの染料を掛け合わせることで、堅牢度も増すのだという。
ライフワークとなった伝統的な衣装の復元
西表島の節祭が、1991年に国の重要無形民俗文化財に指定されたのを機会に、昭子さんは本格的に衣装の復元に着手した。神女とミルクの衣装からはじまり、以後、船頭、船子の衣装などをつぎつぎに復元していき、気がつくと30年たっていた。石垣昭子さんにとって、村の伝統行事で使う衣装の復元はもはやライフワークとなり、今後もしばらく続きそうだという。
苧麻や芭蕉で復元した衣装を村人に着せると、行事の中で役目が終わったあともみんな脱ぎたがらないのだという。昭子さんとしては、衣装はなるべく傷つけたくないので、早く脱いでくれと願っているのだが、「今日一日は着ていてもいいだろう」いわれてしまうそうだ。やっぱり着ていて気持ちがいいのだろうと思うと、うれしくなると語る。伝統行事では、神女も旗頭も船頭も、村人はそれぞれの衣装を着ることで非日常の世界へ入り込む。「衣」とは非日常へ変身するための大きな役割を果たしているのだろう。
沖縄の染織に宿る「ミヌパナ・ティヌパナ」の精神
八重山地方の女性は、昔からミルクの衣装も自分たちの服も作っていた。男達は米を作り豊年祭で奉納をする。それと同じように、家族と自分に着せるものを作ることが、女性にとっての奉納なのだと昭子さんは考えている。
この地方の言葉に「ミヌパナ・ティヌパナ」という言葉ある。ティヌパナとは手仕事のことで、ミヌパナは精神。パナは花のこと。ティヌパナを咲かすためにはミヌパナが必要なのだという。つまり心のない手仕事では花は咲かないというような意味らしい。技術は受けつがれていっても「ミヌパナ・ティヌパナ」の精神が消えかかっていると昭子さんは嘆く。沖縄の染織がいいといわれるのは、そうした精神が布の中に存在するからなのだろう。布を触れたときに、人はミヌパナを知らず知らずのうちに感じ取っているのかもしれない。