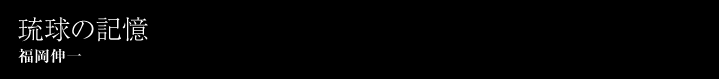![]()
2010.06.18
在来種の豚アグー
小腹がすいてきたので、沖縄そばの店に入った。ここの沖縄そばは普通のものと一風、見た目がちがう。火であぶった脂身の多いソーキは別のお皿にのって出てくる。そばは透明なスープで、上にはうす焼き卵、そこにわけぎが散らしてある。あついスープを一口飲むと薄味ながらこくがあり、甘いうまみがひろがった。「アグーでとっただしなんです」
店のオーナーはこんな風に話してくれた。「おじいさんおばあさんが今の沖縄そばを食べると必ず、昔はもっとおいしかった、というんですよ。それは単にノスタルジーだけではないと思ったんです。そこで昔、どうやってスープをとっていたのかいろいろ調べ始めたんです。そうして行き着いたのが、沖縄の在来種の豚、アグーだったんです。アグーは昔は、そこらじゅうで飼われていた。真っ黒で小柄な身体。弓なりになった背中。しっかり地に着いたかかと。
戦後、大型で成長が早く、肉がたくさん取れ、産仔数も多いヨークシャー、ランドレース、デュロックなどの外国産豚が導入されると、次第に、脂身が多く、小型で、成長に時間がかかり、産む子供の数も少なめのアグーは次第に廃れていった。
そのアグーがここへきて再び評価されるようになってきたのです。もともとラードを取るための豚だったので皮の下に脂身がたくさんあります。でもこれがうま味を出すんです。コレステロールは意外に低く、アミノ酸が豊富で、独特の甘みを出すんです」そう彼は言った。
確かに。アグーだしの沖縄そばはとてもおいしかった。
残り30頭からの復活
 取材中、豚たちは福岡さんを興味深げに眺め、
取材中、豚たちは福岡さんを興味深げに眺め、
ちかよっても逃げずに、好奇心にあふれていました。
黒く、背中が湾曲し、剛毛、短足、副蹄が地に着く、
尻尾は巻いていない、耳は半分、
あるいは全部垂れているのがアグーの特徴です。
 生後数日のアグー。
生後数日のアグー。
お母さん豚は、哺乳の際に横たわるとき、
子豚が自分の下敷きにならないよう細心の注意を払い、
子豚たちは自分が吸う乳首が決まっているそうです。
いったん廃れかけたアグーはどのようにして再び復興されたのだろうか。もちろんそこには特別な人々の気づきがあり、たゆまぬ試行錯誤があり、持続する意思があった。
島袋正敏さんは、農家の生まれだったが、いや、おそらくそれゆえに、生まれながらのナチュラリストだった。風の音や空の光が好きだった。自分の郷土にずっと関心があった。やがて彼は名護博物館の設立に携わるようになり、琉球在来の文化資源にますます興味を持つようになる。トゥラー(琉球犬)、アカマヤー(赤毛の琉球猫)、宮古馬、与那国馬、ヒージャー(在来ヤギ)、チャン(在来鶏)など。その中でも彼はとくに在来の豚、アグーがどうなっているのか気がかりだった。1981年のことである。調べてみると在来のアグーはたった30頭しか確認できなかった。そのうち彼が収集できたのは18頭。なんとか維持したいと思った。
島袋さんの思いに反して、金にならないアグー豚の復興に関心を示す人はほとんどおらず、そんなことをして一体何になるのかと非難までされた。そんなとき救いの手を差し伸べてくれたのが北部農林高校の教員、太田朝憲先生だった。高校には家畜を飼う広い農場があり、豚舎もあった。あと必要なのはたゆまぬ情熱だけだった。集められたアグーの系譜はしかし、その時点で定かなものは何もなかった。在来アグーの純度を高めるための方法はひとつしかない。戻し交配によって近交系をつくること。これは実験動物に対してだけしか行えない。戻し交配とは、母親が産んだ子供が成長したあと、その中からアグーの特徴を持つ個体を選抜し、もういちど母親と番わせること。そうするとアグーの血が濃くなる。これを繰り返す。血が濃くなると問題も起こりやすい。劣性の遺伝子が重なることによって異常や奇形が出やすくなる。だからこそ面倒な交配を注意深く繰り返し、元気なアグー豚を選抜するには時間がかかる。
太田先生の周囲には彼を慕う生徒たちが集まった。彼らのひたむきな努力によって徐々にアグーの系統は安定し、その子孫は増えていった。アグーに関心をもつ畜産家も現れ、北農産アグーは分与され、飼育法にも工夫が重ねられた。
風土の上に成り立つ知恵
北農産のアグー豚は、現在、年間100頭あまりの生産量があり、道の駅や特別に契約を結んだホテルの限定食材として出荷されている。そして今、アグーの飼育を支え、広めているのは、かつての太田先生の生徒たちだ。彼らは教員となって母校に戻り、また新しい生徒たちにアグーの飼育法を継承している。
豚には知恵があった。ヒトにも知恵があった。大昔のある時点で、ヒトと豚は契約を結んだのだ。そしてお互いに安定した暮らしを得た。私たちは豚を愛するがゆえに、豚をそばにおき、そしておいしく豚を食べた。両者は、昔からアグー豚を復興した今現在にいたるまで、この地で絶え間のない相互作用を繰り返してきた。それはこれからも続くだろう。
知恵とは時計仕掛けではない(wise is not clockwise)。知恵とは、ここ沖縄という風土の上に成り立つ動的な平衡なのだ。
(Coyote No43「豚をめぐる冒険」より)